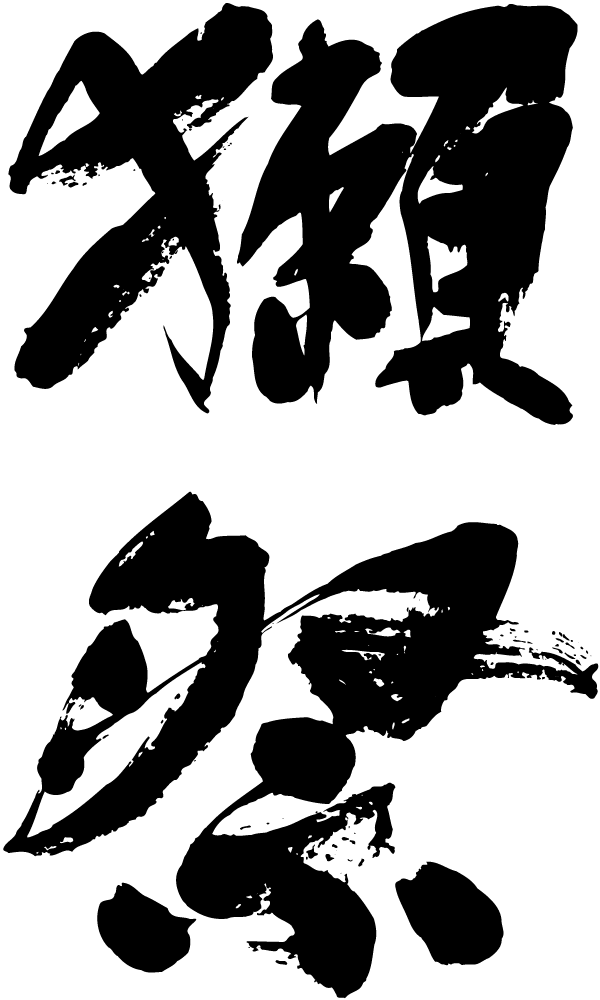獺祭 登龍門 鈴木×荒畑ペア、ご予約開始です!
平素より獺祭WEBストアをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
日中はまだセミの声が聞こえ、夏の名残を感じる一方で、夜には虫の音が響き、少しずつ秋の気配を感じます。
とはいえ、急な雷雨に見舞われる日もあり、なかなか落ち着かない天気が続いていますね。どうぞ体調など崩されませんよう、ご自愛ください。
さて、獺祭 登龍門( 鈴木・荒畑ペア)のご予約を開始いたしました!
今回は、担当した鈴木さんにお話を聞いてみました。
今回のペア
すずき きよあき ・ あらはた かずき
鈴木 白彬 (28) ・ 荒畑 和紀(25)

鈴木 白彬 (写真左) / 28歳 / 香川県出身 / 勤続 7年目 / 所属 発酵管理
荒畑 和紀 (写真右) / 25歳 / 東京都出身 / 勤続 3年目 / 所属 上槽
― 登龍門の仕込みに参加したときの率直な気持ちは?
最初に聞いた時、驚きや緊張はありませんでしたが、次に造るお酒に対する期待と興奮は絶えずありました。
私は昨年7月から12月まで獺祭の営業研修を行い、多くのお客様と接する中で、「より美味しい獺祭とはどんな味なのか」を考えるようになりました。
そんな折、ある酒販店の方から「鈴木君が造った酒を飲んでみたい」と言っていただき、営業研修の経験を活かした酒造りへの想いが強くなりました。
製造部長に掛け合い、営業研修終了のタイミングで“登龍門”としての酒造りがスタート。
自分の実力と、理想の味にどこまで近づけるか、という期待で登龍門は始まりました。

― 「登龍門」が完成したとき、誰に一番最初に知らせましたか?
私の親や友人、お世話になった大学の先生にもお知らせしました。そして、飲んでいただいたところ、美味しいと言っていただけました。
― 香り・味・余韻の中で、今回一番こだわったポイントは?
今回は「味」にこだわりを持って取り組みました。
登龍門のペアが発表されたとき、まず最初に二人で「今回は味にこだわっていこう」と話し合いました。
味のバランスはもちろんですが、特に“きれいさ”や“キレ”をしっかりと感じられること、そして甘味も重たくなりすぎず、すっと抜けていくような味わいにしていこうと決めていました。
香りに関しても、獺祭らしさを大切にしつつ、強すぎず弱すぎず、バランスの取れた香りを目指して造りました。

―「一番やってよかった」と感じた瞬間は?
一番「やって良かった」と思う瞬間は、最初に会長・社長・製造部長から「登龍門として出していい」と承認をいただいた時です。
獺祭では毎朝、前日に搾ったお酒の利き酒を行っています。これは、数値やデータでお酒の管理を徹底しているからこそ、最終チェックは人の舌で行う--という考えに基づいています。
どれだけ狙った数値が出ていたとしても、「獺祭らしく、美味しく」なければ意味がありません。ここを通過することで、初めて「獺祭のお酒」として認められるのです。
登龍門はこれまでに4回行ってきましたが、いつもの最終ジャッジの利き酒は、毎回緊張していました。自信がなかったわけではありませんが、「本当にうまくいったのか」「自分が思っている味がちゃんと伝わるのか」という不安は常にありました。
そんな中で、会長・社長・製造部長に飲んでいただき、「飲みやすくキレがあり、登龍門としてはいい出来ではないか」とコメントをいただきました。この瞬間、本当にやってきて良かったと心から思いました。
そして、その登龍門を瓶に詰め、飲食店での獺祭の会や、来社されたお客様、イベントなどで、多くの方に私が造った登龍門を注いでいきました。
皆さんからは、「後味のキレがあって飲みやすい」「優しい味わいだからこそ飲み続けられる」「ちょうど良い甘さにお酒の華やかさがある」など、多くのコメントをいただきました。
また、私の親や友人にもお酒を送り、「美味しい」と言ってもらえたことも、本当に嬉しかったです。
多くの方に喜んでいただき、ここまでやってきて本当に良かったと、心から感じました。
― 自分たちの“登龍門”は、他の獺祭とどう違うと思いますか?
登龍門の精米歩合は三割九分です。我々の登龍門の味のベースはこの三割九分ですが、その特徴を活かしつつ、より清らかさや後味のキレ、甘味とのバランスが取れた味わいに仕上げています。また、香りが強すぎるとお料理の邪魔になると考え、強すぎず弱すぎず、ちょうど良いバランスを目指しました。
― 「普通の獺祭を造れ」というテーマに、どう向き合いましたか?
獺祭の中で決められていること(精米、酵母、仕込み量など)は変えず、かつ「獺祭らしさ」を残していく。そこが、今回私たちが作った“普通の獺祭”の解釈につながっていくのだと思います。
私も入社して7年目になりますが、「ここを変えてしまったら獺祭らしさが失われる」ということは分かっているため、大きく変えないように意識してきました。
しかしながら、やはり酒造りにおいて相手にするのは“生き物”ですから、いつも予定外のことが起こります。そういった事態には、その都度、軌道修正を加えて対応しなければなりません。

― 今回の仕込みで「一番苦労したこと」は何でしたか?
まず初めに、米麹造りの難しさを改めて感じました。
お酒の製造工程の中でも、米麹は味に最も大きな影響を与えると言われるほど、重要な要素です。私自身も、獺祭で米麹造り(製麹)の工程を約4年間担当しておりました。
しかし今回使用したのは、2024年産の兵庫県産米でした。私の経験上、米の年産や産地が変わるだけで、米麹の出来具合は大きく変わってしまいます。実際、今回はその違いを強く感じました。
また、通常の獺祭では白米量(吸水前の米の重量)1,200kgで米麹を仕込むのに対し、「登龍門」では45kgと90kgの2回に分けて仕込みます。このように仕込み量が少ない場合、室内の温度や湿度の影響を受けやすく、細かな調整が必要となります。環境の違いを十分に考慮した上で作業を行いました。
実はこれまでに登龍門を4回経験しており、今回が5回目の挑戦です。しかし、少量仕込みならではの難しさは、何度やっても慣れるものではありません。今回も経験と知識を活かしながら対応し、最終的には自分が思い描いていた通りの米麹に仕上げることができました。
また、話が重複してしまいますが、「酛立て」(小さなタンクで酵母を増やす工程)や「発酵管理」(大きなタンクでのアルコール発酵)も非常に難しいものでした。
登龍門を4回行う中で、毎回この二つの工程には課題があり、「こうした方がいいのでは」と考えながら試行錯誤を重ねてきました。
通常の獺祭では、仕込み量は1,000kgが一般的ですが、登龍門では600kgで仕込みます。仕込み量が少なくなるほど、温度管理の難易度が上がります。そのため、通常業務の合間にも、ペアを組んでいた荒畑と一緒に、何度も温度確認に足を運びました。
また、どちらかが休みのときには、その日の朝と昼の品温を必ず報告し合い、情報を共有していました。二人で丁寧に温度を確認し、ミスが起きないよう徹底して対応してきたことが、今回の成功につながったと思っています。

― 一緒に仕込んだペアのパートナーをどう感じましたか?
今回の登龍門では、入社3年目の荒畑がペアでした。彼にとっては初めての登龍門で、私が指導しながら一緒に造っていきました。
荒畑の印象としては、一つひとつの作業に非常にひたむきで、教えたことの中で分からない点があれば、すぐに質問をしてくる素直さがありました。また、登龍門を進める中で何らかの課題を提示した際には、自分の意見をしっかりと持って発言できる姿勢も印象的でした。
これまで登龍門を担当してきた中で、私の立場は基本的に“教える側”であり、問題提起をしても相手から意見が返ってこないという場面も少なくありませんでした。これは、どうしても経験や知識の差によるものだと感じており、ある程度は仕方のないことだと思っていました。しかし荒畑は、提示した課題に対して自分なりにしっかりと理解を深めたうえで、自分の考えを伝えてくれる貴重な存在でした。
登龍門は、一人では造れません。やはり二人で造るものです。どちらか一方が任せきりになってしまうと、それは「二人で造った」とは言えません。その点、今回の荒畑とのペアは非常に相性が良く、お互いが責任を持って取り組めたことで、とてもやりやすかったと感じています。彼が今後、どのように登龍門を進化させていくのかが楽しみです。
また、荒畑は私があまり経験してこなかった工程について、深い知識を持っていました。それが「洗米」と「上槽(じょうそう)」です。
洗米に関しては、米の年産や産地が変わるだけで、吸水時間が大きく変わってきます。これは長く洗米を担当していなければ、なかなか感覚として掴めない部分です。酒造りの全工程は洗米から始まるため、ここでの吸水が目標よりも高すぎたり低すぎたりすると、最初からつまずくことになります。今回、彼がいてくれたおかげで、洗米は非常にスムーズに進み、失敗なく行うことができました。
また、酒を搾る「上槽」の工程においても、獺祭ではヤブタ式ろ過圧搾機を使用していますが、機械によって若干の違いが出ることがあります。荒畑から、「今回は○番の圧搾機で搾ったほうがよい」と具体的な提案があり、それに従ったことで、上槽も上手くいきました。

― この酒を飲んだ人に、“どんな気持ち”になってほしいですか?
飲んでいただいて、やはり美味しいと感じていただけることが何よりも大切だと考えています。やはりそこを目指して登龍門の酒造りに取り組んできました。
― 最後に、お客様へのメッセージをお願いします。
この度、鈴木・荒畑ペアの登龍門をご案内できることを嬉しく思います。
「美味しい」と感じていただけるお酒を目指し、二人で力を合わせて丁寧に仕込みました。
私自身、登龍門は回を重ねるごとに美味しくなり、全体のレベルも着実に上がってきていると感じております。 今回の登龍門は、私が造ってきた中でも一つの「美味しい」という答えのかたちでありながら、まだまだ上を目指していける“通過点”でもあります。
このお酒が世に出て、さまざまな場面でお楽しみいただけることを、心より願っております。 そして今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、獺祭をどうぞよろしくお願い申し上げます。
【商品情報】

純米大吟醸 獺祭 登龍門
(精米歩合39%)
■予約期間:9月18日~9月25日
■お届け予定日:9月26日~9月30日
※天候や交通事情によって遅れが生じる可能性がございます。
※獺祭 登龍門は2人でも十分に管理の行き届く量のみを仕込んでいるため、造り出されるお酒の量が非常に限られています。そのため、予約販売でご案内させていただいております。
※ご予約期間内であっても、完売となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※お届け日のご指定を承ることが出来ません。また、その他の商品と合わせてご注文いただく場合のお届けも、9/26~9/30とさせていただきます。何卒ご理解いただきます様お願いいたします。
獺祭 登龍門 について…
若き蔵人が2人1組となり、洗米から上槽(搾り)までの造りの工程全てに取り組みます。蔵人として培ってきた技・知識を表現し、一人前の「獺祭の匠」となるための1つの通過点として「獺祭 登龍門」は存在しています。
過去のペアの取り組みについては公式ホームページで公開しています。若き蔵人の熱い想いを是非ご覧ください!